医療法人鉄蕉会 亀田ファミリークリニック館山 院長 岡田 唯男 先生
ご略歴1995年 神戸大学医学部 卒業
1997年 ピッツバーグ大学メディカルセンター附属シェイディサイド病院
家庭医療学レジデント(米国ペンシルバニア州ピッツバーグ)
2000年 ピッツバーグ大学メディカルセンター 家庭医療学レジデンシー連合会
医学教育者養成プログラムフェロー(米国ピッツバーグ)
2000年 ピッツバーグ大学公衆衛生大学院(公衆衛生学修士取得)
2002年 亀田メディカルセンター 家庭医診療科部長代理
2005年 同 家庭医診療科部長
2006年 亀田ファミリークリニック館山 院長/鉄蕉会 理事
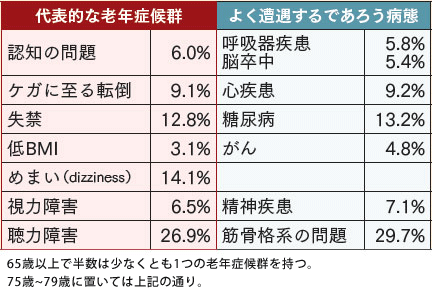
皆さん、高齢者によく起きる問題とは何でしょうか。脳卒中? がん? 糖尿病?……。 図の左側は「老年症候群」の代表的なものです。皆さんが「よく遭遇する」と認識しているであろう右側の病態の出現頻度と比べてみてください。この図によれば、 「糖尿病と同じぐらい失禁と」あるいは「がんと同じくらい低栄養と」向き合わなければ疾患を見過ごすことになります。皆さんは、「がん」に向き合うのと同じ重み(頻度)で「低栄養」と向き合えているでしょうか? プライマリ・ケアをきちんと実践するには従来の「内科」の枠組みだけでは不十分なのです。 今回の企画は高齢者を包括的に診療するため、CGA(高齢者総合評価)とポリファーマシーへの取り組みを総論、内科以外の老年症候群の主要な疾患を各論とし、系統的に学べるよう計画しました。昨年度と 同様、「すぐに紹介」「待機的に紹介」「実地医科で対応可」の3軸に分かりやすくまとめてお伝えします。

杏林大学医学部 精神神経科 助教 今村 弥生先生
ご略歴2002年 札幌医科大学 卒業
2003年 札幌医科大学付属病院 精神科
2007年 浦河赤十字病院精神科
2010年 聖隷三方原病院
2010年 東京都立松沢病院精神科
2014年 日本社会事業大学 非常勤講師
自治医科大学 非常勤講師
2015年 杏林大学医学部 精神神経科
◆◇『認知症・うつ』講義内容◇◆ 高齢者医療の中の精神疾患について、認知症とうつ症状を中心にわかりやすくかつ実践的に講義します。 まず内科・プライマリケアで抱え込むべきではない「すぐに紹介すべき症候」「待機的に紹介すべき症候」について、入院前提の紹介の際のポイントを含めて抑えていただき、実地医科で対応可能な症例については、限界を見据えた薬物療法、高齢者特有の背景にも配慮した心理療法などのトピックスを予定しています。 ※講義内容は変更になる場合がございます

横浜市立大学附属市民総合医療センター リハビリテーション科診療講師 若林 秀隆 先生
ご略歴1995年 横浜市立大学医学部卒業
1995年 日本赤十字社医療センター内科研修医
1997年 横浜市立大学医学部附属病院リハビリテーション科
1998年 横浜市総合リハビリテーションセンターリハビリテーション科
2000年 横浜市立脳血管医療センターリハビリテーション科
2002年 済生会横浜市南部病院リハビリテーション科医長
2008年 横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科助教
2015年 横浜市立大学附属市民総合医療センターリハビリテーション科診療講師
◆◇『転倒・低栄養』講義内容◇◆ 骨折・転倒は寝たきりの主な原因の1つですので、転倒予防の考え方が大切です。転倒予防には、自立歩行可能な高齢者では長期運動プログラムが有用です。フレイル高齢者では家庭環境を調整しながら、可能な範囲内で運動することが有用です。低栄養、サルコペニア、ビタミンD欠乏の場合には、栄養介入が有用な可能性があります。低栄養は高齢者のフレイルや障害の一因であり、栄養改善で身体機能やADLを改善できることがあります。 講義内容は ・転倒リスクの評価と包括的対応 ・低栄養・サルコペニアの評価と包括的対応 ・リハビリテーション栄養 となります。診療時にできる評価と介入について紹介します。 ※講義内容は変更になる場合がございます

独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター 産婦人科 水谷 佳敬 先生
ご略歴2006年 東邦大学卒
2006年 財団法人 警友会けいゆう病院初期臨床研修医
2008年 医療法人 鉄蕉会亀田総合病院/亀田ファミリークリニック館山
家庭医診療科後期臨床研修医
2011年 同フェローシップ
2012年 独立行政法人国立病院機構 長崎医療センター産婦人科
◆◇『失禁・婦人科』講義内容◇◆ 高齢者において、失禁は非常に身近な問題ですが、相談をためらったり、問題が表面化しにくい傾向があります。また、女性は男性に比べて尿道が短く直線的であるため頻度が高く、骨盤底筋群が弱く骨盤臓器脱なども伴い背景も複雑な傾向があります。子宮脱をはじめとした骨盤臓器脱は、相談をためらわれることも多く、排尿に関したQOLの低下にとどまらず、尿路閉塞による尿路感染症・敗血症性ショックで救急受診される事例も見受けられます。高齢者の失禁や骨盤臓器脱のケアについて、日常診療のTipsを加えたのレビューを行います。(男性の尿失禁も扱います。) ※講義内容は変更になる場合がございます

洛和会丸太町病院 救急総合診療科 医長 上田 剛士先生
ご略歴2002年 国立名古屋大学医学部医学科 卒業
名古屋掖済会病院 研修医
2004年 名古屋掖済会病院 救急専属医
2005年 京都医療センター 総合内科 レジデント
2006年 洛和会音羽病院 総合診療科 医員
2010年 洛和会丸太町病院 救急総合診療科 医員
2012年 洛和会丸太町病院 救急総合診療科 医長
◆◇『めまい』講義内容◇◆ めまいの診療が苦手という人も多いですが、めまいの診療では役立つ身体診察が沢山あります。それさえ知ってしまえばもう めまい は怖くありません。今回はめまいの診療に役立つ身体診察をダイジェストでお届けします。 1. 頭位性と体位性の違いを知る 2. 良性発作性頭位性めまい症の診断と治療 ~Dix-Hallpike法とEpley法~ 3. めまいの性状ではなく、眼振の有無で分ける 4. 持続的眼振ではHINTSで脳梗塞を否定する ※講義内容は変更になる場合がございます

京都大学 医学教育推進センター 京都府立医科大学 眼科学教室 加藤 浩晃先生
ご略歴2007年 浜松医科大学医学部医学科 卒業
2007年 京都府立医科大学附属病院 初期研修医
2009年 京都府立医科大学附属病院 眼科 研修医
2010年 バプテスト眼科クリニック 眼科医員
2013年 京都府立医科大学大学院 視覚機能再生外科学(眼科)
2014年 京都大学 医学教育推進センター
◆◇『視力障害』講義内容◇◆ 高齢者の視力障害を『進行のスピード』から「緩徐な視力低下を訴える疾患」と「急性の視力低下を訴える疾患」に分類して整理します。 頻度や緊急度からぞれぞれの代表疾患をピックアップして、疾患の概要だけでなく対応や患者説明のポイント、眼科紹介のタイミングについてもまとめていきます。 ● 緩徐な視力低下を訴える疾患 :白内障、加齢黄斑変性 など ● 急性の視力低下を訴える疾患 :網膜中心動脈閉塞症(CRAO)、急性緑内障発作 など ● 視力低下をきたす疾患の対応と眼科紹介のタイミング ※講義内容は変更になる場合がございます

医療法人鉄蕉会 亀田メディカルセンター スポーツ医学科 医長 服部 惣一 先生
ご略歴2004年 東海大学医学部医学科 卒業
2004年 亀田メディカルセンター 初期研修医
2006年 亀田メディカルセンター 救命救急科 後期研修医
2009年 亀田メディカルセンター 整形外科
2012年 亀田メディカルセンター スポーツ医学科
2013年 亀田メディカルセンター スポーツ医学科 医長
コメント ◆◇講義内容◇◆プライマリケアの先生方が診療されているセッティングは様々であります。先生方が持っている医療資源を最大活用し、高齢者の腰痛・膝痛診察のレベルを上げましょう。
- 初段:紹介した方がいい?大丈夫?の見分け方
- 弐段:鎮痛薬の活用
- 参段:超音波(エコー)の活用
- 四段:リハビリの活用
- 十段:レントゲン写真の活用

